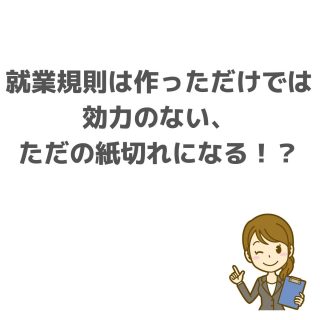コンプライアンスや人権への関心が高い現代では、会社経営においてハラスメント問題は無視できない重要な課題となっています。
ハラスメントが発生している職場では、従業員のモチベーションが低下し、業績に悪影響をおよぼすのはもちろんのこと、法的なリスクも伴います。
そのため、特に中小企業では、限られたリソースの中で従業員の働きやすい環境を整えるため、効果的なハラスメント対策が不可欠です。
そこで、この記事では、中小企業が取り組むべき具体的なハラスメント対策について、具体例を交えて解説します。
中小企業のハラスメント対策の重要性

ハラスメントが会社におよぼす影響
ハラスメントは、従業員の心身に深刻な影響をおよぼすだけでなく、企業全体にも大きな悪影響をもたらします。
具体的には、以下のような影響が想定されます。
- 被害者のストレスや不安が増大し、健康を損ねるリスクが高まる
⇒仕事のパフォーマンスが低下し、長期的な病気や離職につながることがある - 職場全体の士気が低下し、従業員間の信頼関係が崩れ、チームワークが損なわれる
⇒生産性が低下し、顧客サービスの質も悪化し顧客離れにつながることがある - ハラスメントの事実が外部に漏れることで、企業の評判が悪くなる
⇒顧客や取引先からの信頼を失い顧客離れにつながることがある
最悪の場合は、訴訟に発展し、慰謝料の支払いや損害賠償を命じられる可能性もあります。このように、ハラスメントは会社に多大な影響をおよぼすため、早期に対策を講じることが不可欠です。
ハラスメントに対する法的な義務と会社の責任
ハラスメントには多くの種類がありますが、一部のハラスメントについては、そのハラスメント防止のための措置を講じることが法律で義務とされています。
具体的には、
- セクシャルハラスメント(セクハラ)
- 妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント(マタニティハラスメント(マタハラ))
- パワーハラスメント(パワハラ)
が対象となっています。
これらのハラスメント対策のため、会社としてハラスメントへの方針を示すことや、相談窓口の設置などが求められています。
また、会社のハラスメントへの対策が不十分でハラスメントが発生し、被害者が出てしまった場合は、会社の安全配慮義務違反を問われる可能性もあります。
企業文化の醸成と維持
ハラスメント対策を効果的に行うためには、法的義務を果たすことはもちろんですが、その前提として、ハラスメントを許さない、起こさせない企業文化の醸成と維持が重要です。
特にハラスメント防止の観点からは、従業員同士がお互いを尊重し、協力し合う文化を育むことが大切です。
理想的な組織文化を創っていくためには、以下のような方法が考えられるでしょう。
- 定期的なミーティングやワークショップをとおして、従業員が互いに意見を交換し、問題を共有する場を設ける
- 経営者をはじめとして、リーダー層が率先してハラスメント防止の取り組みを推進する
※中小企業の場合は、特に経営者やリーダー層の言動が、そのまま企業文化として醸成されていきます。 - 従業員からの意見やフィードバックを積極的に取り入れる
このような取り組みをとおして健全な企業文化が創られることで、ハラスメントの発生が抑えられ、従業員が安心して働ける環境が整っていきます。
より良い組織づくりの取り組みを行うことが、結果的にハラスメント対策になります。
ハラスメントの種類と特徴

職場のハラスメントの種類
職場で発生するハラスメントには多くの種類がありますが、代表的なものを挙げてみます。
- セクシャルハラスメント(セクハラ)
性的な言動や行為によって他人を不快にさせる行為を指し、女性だけでなく男性も被害者となり得ます。また、異性間だけではなく、同性間でも対象となります。 - パワーハラスメント(パワハラ)
主に職場の権力関係を背景に、上司が部下に対して行う精神的・身体的な嫌がらせやいじめを指します。※部下から上司への言動でもパワハラに該当する可能性はあります。 - 妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント(マタニティハラスメント(マタハラ))
妊娠・出産したこと、産前産後休業・育児休業などの制度利用を希望したことや、実際に制度を利用したことなどを理由として、同僚や上司等が嫌がらせなどを行うことです。 - モラルハラスメント(モラハラ)
言動や態度などで相手に精神的苦痛を与えて、相手の人格を否定するなどの行為です。 - ハラスメント・ハラスメント(ハラハラ)
業務上通常の行為に対して過度に反応し、ハラスメントであると主張して相手を困らせる嫌がらなどを行うことです。
上記以外にも多種多様なハラスメントが存在しています。
最近は顧客や取引先から受けるカスタマーハラスメント(カスハラ)も問題となっており、このようなハラスメントから従業員をいかに守っていくのかも大切な労務管理の一つとなっています。
なぜハラスメントは見逃されやすいのか?
ハラスメントは必ずしも目に見える形で発生するわけではありませんので、発生初期の段階では見逃されやすい兆候があります。
例えば、ハラスメントの種類によって見逃されやすい理由があります。
- セクハラの場合
被害者が相談や報告をためらってしまうことが多いため、周囲の従業員が気づきにくいことがあります。 - パワハラの場合
主に上司と部下という関係性から、業務上の注意や指導と嫌がらせの区別がつきにくいことがあり、問題が見過ごされることが多いです。 - モラハラの場合
言葉の暴力や精神的な圧力を伴うため、外見上は普通のコミュニケーションのように見えることがあるため、見過ごされやすいです。 - すべてのハラスメントに共通する理由
ハラスメントに対する知識が不足しているため、加害者側も被害者側も当初はハラスメントとして認識していないため、行為が長期化・深刻化してしまうことがあります。
ハラスメントの兆候を見逃さないためには、定期的な従業員アンケートや面談を通じて職場の雰囲気を把握し、早期発見に努めることが重要です。
そのためには、従業員が安心して相談できる環境を整えることが必要不可欠です。
ハラスメント対策の具体例

ハラスメントに対する方針の明確化
ハラスメント対策を効果的に行うためには、明確な方針を打ち出すことが不可欠です。
口頭だけではなく書面やPDFファイルなどで、ハラスメント対策の基本方針を明記し、全従業員に周知徹底する必要があります。
具体的には、ハラスメントが許されない職場環境の構築を目指すことを宣言し、従業員一人ひとりが対策の重要性を理解するよう促します。
また、新入社員に対しても入社時にこの方針の説明を行い、全員が同じ認識を持つようにすることが重要です。
明確なルールの策定と運用
ハラスメント対策において、明確な規程(ルール)の策定と運用が欠かせません。
ハラスメント防止のための具体的なルールを「ハラスメント防止規程」などとして策定し、それを全従業員に周知徹底する必要があります。
規程には、ハラスメントの定義、禁止行為、報告手順、調査方法、処分の基準などを明記し、従業員が理解しやすい言葉や表現で策定することが重要です。
そのうえで、以下の取り組みをしていくと良いでしょう。
- 規程の運用を始める前に、従業員に対する教育や研修をとおして規程の内容を周知します。
- 実際にハラスメントが発生した際には、規程に基づいて迅速かつ公平な対応を行い、被害者の保護と再発防止を図ります。
- 実際に運用してみて、運用が難しい規定がある場合や、法改正・社会情勢の変化に応じて規定の見直しを行います。そのためには、定期的に規程をチェックする必要があります。
相談窓口の設置と運用

ハラスメントが発生した際に従業員が安心して相談できる環境を整えることも重要です。
※法律でも相談体制の整備は義務とされています。
相談窓口を設置・運用していく際には、以下のポイントに注意が必要です。
- 適切な教育を受けた相談員を配置する。
- 定期的に相談員のスキルアップ研修を実施し、最新の法的知識や対応方法を習得させる。
- 相談窓口の運営においては、プライバシーの保護を徹底し、相談内容が外部に漏れないようにすることが不可欠。
- 匿名での相談が可能な仕組みを導入することを検討する。
- 社内文書などで相談窓口の存在を周知徹底し、従業員が利用しやすい環境を作る。
社内で相談窓口を設置することが難しい場合は、外部の相談窓口に依頼することを検討します。
効果的なハラスメント研修の実施
研修では、ハラスメントの定義や種類、法的な背景を具体的に説明することが重要です。
また、具体的な事例を交えながら、どのような行動がハラスメントに該当するかを示すことで、従業員が自身の行動を見直すきっかけとなります。
以下、ハラスメント研修のポイントです。
- ロールプレイングやグループディスカッションを取り入れる。
ハラスメント行為の模擬実演や従業員同士が、ハラスメントへの認識などを話し合う機会を提供することが効果的です。 - 定期的に研修を行う。
繰り返し研修を受けることで、知識や考え方が定着するとともに、ハラスメントへの意識を高めることにつながります。 - 社員の立場によって特別な研修を実施する。
例えば、新入社員や管理職を対象とした特別な研修プログラムを用意することが考えられます。
ハラスメント対策の継続的な改善

対策の定期的な見直しと評価
少なくとも年に1回はハラスメント対策の現状を評価し、必要な改善点を見つけましょう。
評価のために従業員アンケートやヒアリング、相談窓口への報告内容の分析を実施します。これにより、現在の対策がどの程度効果を発揮しているかを客観的に判断できます。
また、法改正や社会情勢の変化にも対応するため、最新の情報チェックすることが必要です。
従業員からのフィードバックを活かして改善する
従業員が日常的に感じている問題や改善点を共有する場を設けることで、現場のリアルな状況を把握できます。
例えば、定期アンケケートの実施や匿名の意見箱を活用して、従業員の声を集めます。
そして、フィードバックの内容を真摯に受け止め、具体的な改善策を迅速に実施することが求められます。
従業員の意見を反映した改善策が実施されれば、従業員の信頼を得ることができますし、全員が改善の重要性を認識し、積極的に協力する姿勢が生まれることが期待できます。
まとめ
ハラスメント対策は、中小企業にとって今後ますます重要な取り組みとなっていきます。
ハラスメントは従業員の健康や士気、企業の生産性に悪影響をおよぼし、法的リスクも伴いますので、早期に対策をとる必要があります。
法律で定められているハラスメント対策を実施することはもちろんですが、この会社で働き続けたいと思えるような組織づくりをしていくことが一番の対策となります。